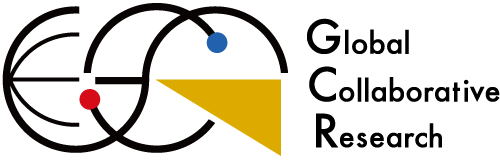インキュベーション・プログラム
「ラオス、ベトナム農山村の植物資源の残存要因に関する探索的研究」
R7-8 1-5 (令和7年度 FY2025 新規)
| 研究代表者 | 広田 勲 (岐阜大学 / 准教授) |
| 共同研究者 | 柳澤 雅之 (東南アジア地域研究研究所 / 准教授) 冨吉 満之 (久留米大学経済学部 / 准教授) 片畑 伸一郎 (岐阜大学応用生物科学部 / 助教) |
| 研究課題 | ラオス、ベトナム農山村の植物資源の残存要因に関する探索的研究 |
| 研究対象国 | ラオス, ベトナム |
研究概要
東南アジア農山村の農地や周辺環境では作物や植物相の単純化が進む一方、多様な有用植物や在来作物が小規模に残存している。本研究は地域研究、農業生態学、農業経済学、植物遺伝学の視点から維持要因を解明し、所持データや先行研究を整理しつつラオスやベトナムを対象に調査や実験を補完的に行う。現地機関と連携して植物資源の保存要因の解明と持続的利用に向けた研究体制を構築することを目指す。
研究目的・意義・期待される効果など
本研究は、東南アジア農村に残る多様な小規模植物資源がどのように維持され、生業にどのように貢献しているのか、またどのように類型化し理解できるのかを、異分野の研究者間の議論を通じて、ラオスやベトナム山地部の農村を事例として探索的に把握することを目的とする。これまで人里周辺の多様な資源利用の発達および維持要因については、生業の不安定性への対応や文化的価値観、主要活動に付随する間接的要因などが影響すると考えられているが、自給的性格の強い資源については外部からは実態が把握されにくく、具体的な検証が不足している。例えば作物品種の維持では、種子の継承や保存方法、栽培方法、植物自体の生殖特性など複合的な要因が関与しているが整理が進んでいない。本研究では、地域研究、農業生態学、農業経済学、植物遺伝学などの専門家が学際的に議論し、マイナーな植物資源の維持に関する社会的・経済的・農学的・植物学的要因を整理する。得られた知見は植物資源多様性維持の具体的情報提供につながり、特にラオスではイネ以外の在来植物情報が不足している現状を補い、現地における生物文化多様性保全に向けた基礎的データを提供できる。