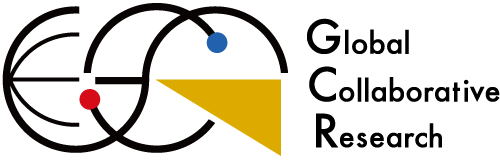パイロット・スタディ・プログラム
「ブータン農村の小規模校における『教育の質』改善のための基礎調査」
R7 2-2 (令和7年度 FY2025)
| 研究代表者 | 森下 航平 (京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 / 大学院生) |
| 研究課題 | ブータン農村の小規模校における「教育の質」改善のための基礎調査 |
| 研究対象国 | ブータン |
研究概要
ブータンは、GNH(国民総幸福)の理念のもと小規模校を普及させてきた歴史を有するが、2010年代に政策は統廃合による規模再編にシフトし、小規模校の課題解決が置き去りになっている。本研究では「ブータン農村で小規模校を維持するため『教育の質』をどのように改善できるか」を明らかにするため、教育現場での参与観察と聞き取り調査を行い、複式指導を含む教育指導と学校運営の実態を調査するとともに、日本や他の東南アジア諸国の研究・実践者との国際協働による課題解決の可能性を探る。
研究目的・意義・期待される効果など
GNHの理念のもと基礎インフラの全国普及を目指すブータンにとって、小規模農村への教育普及は、その限られた財政と山がちな自然環境から大きな課題となってきた。1987年に「拡張教室」と呼ばれる(のちに「コミュニティスクール」とも呼ばれる)簡易的な分校を地域住民の労働で建設する制度を導入したほか、複式指導の普及に取り組んできた。その結果、2009年には初等教育就学率は90%を超えた一方、小規模校の「教育の質」の低さが問題視され、2010年代に小規模校を統廃合し中核校に資本を集中投入する政策へ転換した。統廃合の結果、自宅近くから学校が無くなったため、児童が幼少期から寮生活を余儀なくされる事例が生じている。また子どもとともに保護者も離村する場合があり、農村の持続性への影響が心配される。
一方、中山間地域の小規模校でどのように「教育の質」を確保していくか、日本の教育現場では100年以上にわたり試行錯誤されており、複式学級での指導法や地域住民と協働する学校運営、地域資源を活かしたカリキュラム立案などは優れた成果を挙げてきた。また東南アジアの一部の国では、小規模校での指導改善のための教員養成や教材開発が盛んに実践され、日本による国際教育協力の参画実績もある。本研究では「ブータン農村で小規模校を維持するため『教育の質』をどのように改善できるか」を明らかにするため、教育現場での参与観察と聞き取り調査を行い、複式指導を含む教育指導と学校運営の実態を調査する。また本調査成果を日本や他の東南アジア諸国の研究・実践者と共有し、国際協働による課題解決の可能性を探っていく。