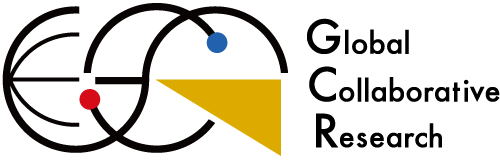パイロット・スタディ・プログラム
「近世と近代の交錯: ベトナム第一国立公文書館所蔵南定省務本県百穀社において起きた事件に関する報告書の概観」
R7 2-1 (令和7年度 FY2025)
| 研究代表者 | 趙 浩衍 (京都大学東南アジア地域研究研究所 / 連携研究員) |
| 研究課題 | 近世と近代の交錯: ベトナム第一国立公文書館所蔵南定省務本県百穀社において起きた事件に関する報告書の概観 |
| 研究対象国 | ベトナム |
研究概要
本研究の対象は、ベトナム第一国立公文書館に所蔵されている南定省務本県旧百穀社(現在のタインロイ(Thành Lợi)およびコックタイン(Cốc Thành)合作社の一部)で発生した事件に関する報告書群である。本研究は、仏領期(1884-1945)に村落で発生した事件を分析することにより、当時の村人の関心事、葛藤、および問題解決の過程を明らかにすることを目的とする。
研究目的・意義・期待される効果など
報告書は、村民による告訴状・陳述書と、行政側の報告書(および判決文)に大別される。前者は漢文あるいは字喃で書かれることが多く、後者はクオック・グーや、内容を簡略化したフランス語訳の形で記される場合が多い。こうした多言語の史料を一字ずつ精査し、報告書を読解・整理する手法を確立することが期待される。さらに、これらの報告書を村落側の資料と総合的に分析することで、仏領期の村落の実像を明らかにし、それが近世から現代へどのように受け継がれ、あるいは変容したのかを提示できると考える。
これらの研究成果の意義は、主に次の二点に集約される。第一に、「支配」と「抵抗」という単純な二項対立に基づく従来の植民地研究の枠組みを超え、現地住民の主体的な対応に着目することで、より実態に即した植民地社会像の再構築を目指す。こうした「ベトナム鏡」に映し出された姿は、国際秩序が転換期を迎える今日において、歴史的和解や新たな関係性の構築に資する視座を提供しうると確信している。第二に、日本で急速に解体された血縁・地縁共同体とは対照的に、ベトナムでは都市化や移住が進む中でも、村落共同体への強い帰属意識が維持されている点に注目する。この点を踏まえ、現代日本社会における共同体再生のヒントを探るとともに、存在感を増す在日ベトナム人コミュニティへの理解を深めたい。