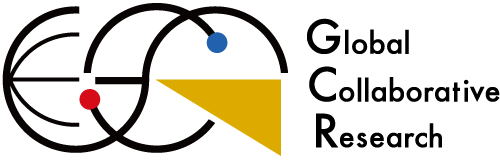地域情報学シード・プログラム
「インドネシア・デジタル沈香研究センターの構築」
R7-8 7-1 (令和7年度 FY2025 新規)
| 研究代表者 | 伊藤 美千穂 (国立医薬品食品衛生研究所・生薬部 / 部長) |
| 共同研究者 | 藤原 裕未 (国際医療福祉大学・成田薬学部/講師) 高松 さくら (愛媛大学大学院農学研究科/研究員) 飯塚 宜子 (京都大学東南アジア地域研究研究所/研究員) 柳澤 雅之 (京都大学東南アジア地域研究研究所/准教授) |
| 研究課題 | インドネシア・デジタル沈香研究センターの構築 |
| 研究対象国 | インドネシア |
研究概要
インドネシアの沈香は資源の枯渇が問題となっている。国際共同研究加速基金「ウォーレシア・パプア域の沈香―種の分布・成分・遺伝資源保全の共同研究」(代表山田勇、2020-2025年)によって進めていた沈香に関する研究活動は、2025年6月の代表者逝去によって即時執行停止となった。本研究では、地域情報学の手法を用い、共同研究によって蓄積された研究成果に基づき、沈香に関するバーチャルな研究センター構築を目的とする。
研究目的・意義・期待される効果など
故山田勇と本申請の代表者・伊藤は、1990年代から沈香の調査を行ってきた。2003年からはマタラム大学のTri博士と共にインドネシア各地の沈香の現地調査をおこなった。この間、天然の沈香資源の枯渇は甚だしく、遺伝資源の保全が喫緊の課題となった。一般に、天然資源の枯渇に対処するためには、遺伝資源に関する探索、現地保全、現地外保全などのマニュアル化が世界の森林関係機関で標準となっている。沈香もまたこうした活動が必須であるにもかかわらず、現在、こうした保全活動をシステマティックに実施している機関・国はない。沈香を多数産出するインドネシアもまた例外ではない。マタラム大学は2000年から沈香研究が始まり、その中心になったのが同大学のTri博士である。同氏は実質的にマタラム大学の沈香に関するすべての研究の中心人物として、現地調査から苗畑、保存温室の設計や研究室の充実化を進めてきた。その過程で、山田勇との共同研究が開始された。しかし、共同研究が完結する前にプロジェクトが強制的に終了され、DNA分析や形態分類の作業がいくつか残された。本研究では、それらの活動を継続することに加えて、沈香に関する成果を、地域情報学の手法を用いて共有化することを目的としている。用いる手法は、柳澤氏によって開発された地域情報学アーカイブである。きわめて簡易な時空間表示システム上で、資源の分布やサンプルのDNAや形態に関する分析結果を示し、沈香に関するバーチャルな研究センターを構築する。枯渇する資源の保存と利用について大きな意義があると考える。

マタラム大学構内に掲示されている沈香研究の成果ポスター。山田、伊藤、Triの名前も見られる。2024年10月撮影。

マタラム大学で実験中の沈香のサンプル写真。穴をあけ菌を植え付けることで沈香成分の発生を促す。2024年10月撮影。