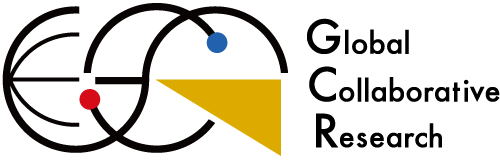フィールド滞在型プログラム
「情報化時代における東南アジアの辺境社会」
R6-7 4-1 (令和7年度 FY2025 継続)
| 研究代表者 | 生方 史数 (岡山大学学術研究院 / 教授) |
| 共同研究者 | 祖田 亮次 (大阪公立大学大学院文学研究科 / 教授) 葉山 アツコ (久留米大学経済学部 / 教授) 小泉 佑介 (一橋大学大学院社会学研究科 / 講師) 小林 知 (京都大学東南アジア地域研究研究所 / 教授) 加反 真帆 (九州大学大学院農学研究院 / 学振特別研究員(PD)) |
| 研究課題 | 情報化時代における東南アジアの辺境社会 |
| 研究対象国 | ベトナム, マレーシア, タイ, インドネシア, フィリピン |
研究概要
情報化社会の波は、焼畑、狩猟採集、漁撈などを営んでいた東南アジアの辺境社会の人々にも及んでいる。特に近年は、国家や市場アクターがSDGsの実践等を契機に情報基盤を整備することで、辺境社会は遠隔地と強力に結合されつつある。このような動きは、情報をより重要なリソースへと押し上げ、辺境地社会に大きな影響を与える可能性がある。本研究では、東南アジア辺境地域における輸出用一次産品の生産・流通や環境保全事業を事例に、国家・市場・地域社会を構成するアクターが各々の情報基盤をどのように拡張したのか、またそれらが現実社会とどのように相互作用しているのかを検討する。
研究目的・意義・期待される効果など
情報化社会の波は、焼畑、狩猟採集、漁撈などを営み近年まで自律性を保っていたといわれる東南アジアの辺境社会にも及んでいる。この地域は独立後に国民国家や市場への統合が進行したといわれるが、最近のSDGsアジェンダとデジタル情報技術の普及は、国家や市場と地域社会との関係性に新たな影響を与えつつある。例えば、気候変動対策としてEUが2023年に導入を決定したEUDRでは、EUに輸出される農産物に森林を破壊していない旨の証明が義務化されることになった。東南アジアでも、パーム油、ゴム、コーヒーなどの主要農産物が、トレーサビリティを確保するための対応を迫られている。
以上のようなデジタル情報を介した国家や市場の影響力の増大は、東南アジア辺境部の地域社会をどうつくりかえるだろうか。本研究では、東南アジア辺境地域における輸出用一次産品の生産・流通や環境保全事業を事例に、国家・市場・地域社会を構成するアクターが各々の情報基盤をどのように拡張したのか、またそれらが現実社会とどのように相互作用しているのかを検討する。
本研究の独自性は、デジタル情報技術の普及やSDGsに地域研究的な視点から接近する点である。すなわち、これらを社会が目指すべき目標としてではなく、むしろ国家や企業がその方針や戦略を都合よく変えるための機会ととらえ、辺境地域ではこれらのアクターと人々との「文化衝突」が起きているという枠組みを設定する。これによって、SDGsの実践が結果的に人々の支配を強化する状況の実態やメカニズムと、それに対して辺境社会が築くべき対応策を明らかにすることができる。