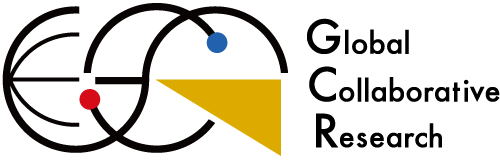インキュベーション・プログラム
「山村の景観形成においてヤマチャが果たした機能の検討にむけた分野横断的研究」
R6-7 1-3 (令和7年度 FY2025 継続)
| 研究代表者 | 佐々木 綾子 (日本大学生物資源科学部 / 専任講師) |
| 共同研究者 | 片岡 樹 (京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 / 教授) 中村 羊一郎 (静岡産業大学 / 元教授) 柳澤 雅之 (京都大学東南アジア地域研究研究所 / 准教授) 大澤 由実 (桜美林大学リベラルアーツ学群 / 准教授) 磯田 真紀 (京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 / 特任研究員) |
| 研究課題 | 山村の景観形成においてヤマチャが果たした機能の検討にむけた分野横断的研究 |
| 研究対象国 | 日本 (四国・九州・北陸) |
研究概要
東南アジア山間地では、自生する「ヤマチャ(山茶)」を意図的に残した「ヤマチャ景観」が形成され、地域史に大きく関与していることが報告されてきた。一方、日本の山村における生業や景観形成とヤマチャとの関連は見過ごされてきた。本研究では、東南アジア地域史との比較に貢献することを視野に入れ、日本の山村におけるヤマチャ景観の形成・変容過程と、生業におけるヤマチャの資源としての機能を検討することを目的とする。
研究目的・意義・期待される効果など
モンスーンアジアの山間地に自生するチャ(チャノキ、Camellia sinensis)は「ヤマチャ(山茶)」と呼称され、様々な利用を通じ山間地における生業・生活の一部をなしてきた。東南アジア大陸部を対象とした研究では、ヤマチャが山間地の生態環境や地域史において重要な役割を果たしていることが示唆されてきた。
一方、日本では、茶の持つ高い文化性から「茶文化」の文脈でヤマチャがとらえられてきた。そのため、一資源としてヤマチャが果たしてきた役割・機能については見過ごされており、日本の山村の地域史・生業の変遷とヤマチャとのかかわりについては検討されてこなかった。そこで本研究では、日本の山村における生業の中で、ヤマチャが資源として果たした機能を検討することを目的とする。これらの議論により、1)日本において特殊に切り出されてきたヤマチャを生業・景観を構成する一資源として位置づけ、さらに2)茶文化研究と地域研究に加え、景観学、経済学、民族植物学の視点から、ヤマチャ研究を景観論として再構築することが期待される。
またヤマチャを伴ういわば「ヤマチャ景観」の形成過程を明らかにするとともに、現在の過疎・高齢化、継続的な資源利用の減少による変化を明らかにすることで、将来的に東南アジア地域史との比較に貢献することを目指す。