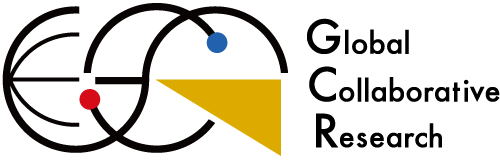インキュベーション・プログラム
「インドネシア・ボロブドゥールのレリーフを中心とした総合的研究」
R7-8 1-6 (令和7年度 FY2025 新規)
| 研究代表者 | 伊藤 奈保子 (広島大学人間社会科学研究科 / 准教授) |
| 共同研究者 | 根本 裕史 (広島大学人間社会科学研究科 / 教授) 小林 知 (京都大学東南アジア地域研究研究所 / 教授) 松浦 史明 (上智大学総合グローバル学部 / 特別研究員) ニケン・ウィラサンティ (UGM:ガジャマダ大学文化研究学部 / 准教授) イナジャティ・アドゥリジャティ (UGM:ガジャマダ大学文化研究学部 / 教授) アクバル・リズキ・ディア・ハビビ (UGM:ガジャマダ大学文化研究学部 / 専任講師) デスタリオ メトゥサーラ (BRIN (The National Research and Inovation Agency) / 研究員) ムハマッツド・レザ・ルスタン (インドネシア大学戦略グローバル学部 / 准教授) ズルフィカル・ラーマン (ブラヴィジャヤ大学日本文学科 / 講師) |
| 研究課題 | インドネシア・ボロブドゥールのレリーフを中心とした総合的研究 |
| 研究対象国 | インドネシア |
研究概要
本研究は、インドネシア中部地域のボロブドゥール遺跡について新しい理解を提出することを目指す。8~9世紀頃建立とされるボロブドゥール遺跡の第2~第4回廊主壁(27面、88面、72面)レリーフを、①尊像、②服制、③装飾、④全体の背景の4つの視点から分類・分析し、尊像の図像・尊名の再検討を行う。それにより、レリーフ彫刻にみられる像の体系化を図ることを第一の目的に置く。次に経典との照合を試みることでこの遺跡の仏教的意義の明確化を目指す。
研究目的・意義・期待される効果など
本研究の目的の1つ目、美術史的考察からボロブドゥールの仏教・特に密教といった宗教をレリーフ考察から導きだす。前回は1927年出版、N.J.Kromの書籍からレリーフ全体の確認及び特徴のあるレリーフの検討を行ったが、今回は順に仏教・密教要素の強い第2~第4回廊主壁『大方広仏華厳経』「入法界品」『普賢行願讃』とされる回廊彫刻、計187 面(27面、88面、72面)を再検討する。また同時期建立のヒンドゥー教寺院、後に伝播したカンボジア美術等との比較研究を各研究者により検討を試みたい。
第二の目的として、学際的な研究であるが、多角的な視点でボロブドゥールを捉える事でこの遺跡の存在意義が導き出せるとして、現地研究者を①レリーフの植物学分類・楽器分類等、舞踊分類等、②土産物店の発生・現状・将来の考察と各国言語の習得方法、観光客の出身地の見分け方等、③コロナ禍での国の施策の分析、入場制限や履き物の徹底、ガイドを付けたグループ制への移行、警備の充実等の3つに分け、現地調査をもとに研究を行う。昨年よりインドネシア大学・ブラヴィジャヤ大学の教員2名が土産物の店主たちより聞取りを始めているが、調査に関する回数を重ねる必要性がわかった。また、コロナ禍以降の国の施策等については、国会図書館等の文献資料の確認が重要と考えられる。