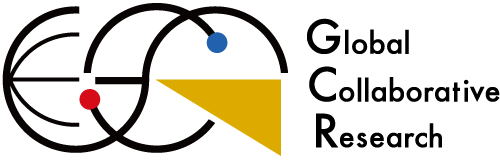インキュベーション・プログラム
「インドネシア神経難病多発地域における⽔環境調査」
R7-8 1-3 (令和7年度 FY2025 新規)
| 研究代表者 | 坂野 晴彦 (京都大学iPS細胞研究所 / 特命准教授) |
| 共同研究者 | 石黒 亮 (法政大学・マイクロ・ナノテクノロジー研究センター / 研究員・客員准教授v 和田 泰三 (医療法人学縁会おおさか往診クリニック / 副院長) 平田 温 (吉田病院附属脳血管研究所脳神経内科 / 脳血管研究所長、脳神経内科部長) 小久保 康昌 (三重大学大学院地域イノベーション学研究科 / 招聘教授) 坂本 龍太 (京都大学東南アジア地域研究研究所 / 准教授) |
| 研究課題 | インドネシア神経難病多発地域における⽔環境調査 |
| 研究対象国 | インドネシア (南パプア州) |
研究概要
インドネシア パプア州では、神経難病の多発が報告された。近年急激に患者数の減少と病型の変化が認められたものの、発症原因は不明である。最近になって筋萎縮性側索硬化症(ALS)の発症機序にリチウム(Li)安定同位体の関与が示唆された。本研究は神経難病多発の原因特定を目的に、当該地域の環境水に含まれるリチウム同位体比を計測する。6Li比の高値が認められれば、高6Li比が神経難病発症を惹起する可能性が高まり、長年不明であった発症原因の謎が解ける。
研究目的・意義・期待される効果など
インドネシア パプア州(現在の南パプア州)では、グアムや紀伊と並び、1970年代に神経難病の多発(世界平均の100倍以上)が報告された。グアムや紀伊は、社会の近代化とともに、急激に神経難病の減少と病型の変化が認められ、インドネシアでも、2001~2019年にかけて京都大学東南アジア地域研究研究所のグループによる調査が行われ、97症例の検討で同様の神経難病の減少と病型の変化が認められた。
一方最近になって、神経難病のうち、特にALSの発症に、リチウム(Li)の安定同位体が関与している可能性が示唆されてきている。通常、リチウムは6Liが7.6%、中性子が1個多い7Liが92.4%存在する。本邦にはLi 同位体比の異常を示す場所が存在する。基礎研究の結果、6Liは7LiよりKやNaと競合し易く、神経細胞の軸策輸送に寄与するグアニン四重鎖の安定化を阻害するため、ALS発症のリスク因子であることが示唆されている。本研究は、神経難病多発の原因特定を目的に、当該地域の環境水に含まれるリチウム同位体比を計測する。もし6Li比が高値であれば、リチウム同位体が神経変性疾患発症を惹起する可能性が高まり、長年不明であった発症原因の謎が解ける。
本研究による環境要因の特定は、当該地域における疾患の克服のみならず、現在治療法のない認知症を含む各種神経変性疾患への新規治療法開発に直結する。