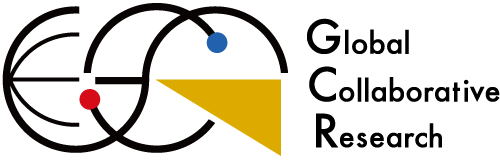インキュベーション・プログラム
「『地べた』の冷戦史: タイとベトナムにおける草の根の文化・国家論」
R7-8 1-1 (令和7年度 FY2025 新規)
| 研究代表者 | 西田 昌之 (東北学院大学 / 准教授) |
| 共同研究者 | 下條 尚志 (神戸大学大学院国際文化学研究科 / 准教授) 片岡 樹 (京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 / 教授) 小田 なら (東京外国語大学大学院総合国際学研究院 / 准教授) 櫻田 智恵 (上智大学総合グローバル学部総合グローバル学科 / 助教) 土屋 喜生 (京都大学大学東南アジア地域研究研究所 / 助教) |
| 研究課題 | 「地べた」の冷戦史: タイとベトナムにおける草の根の文化・国家論 |
| 研究対象国 | ベトナム, タイ, カンボジア, 東南アジア島嶼部 |
研究概要
本研究はタイとベトナムを軸に据え、冷戦期の文化と国家について歴史的な並行性と連動性を捉える試みである。それによって日常を生きる人々の歴史体験に真摯に向き合う「地べた(on the ground)」の冷戦史を示す。本研究では、各々の社会に歴史的に埋め込まれた諸文化的要素(e.g. 宗教儀礼、伝統医療、山茶栽培、王の行幸)に注目し、国家や民族、宗教、階層、イデオロギーの分断線を越え、東南アジアの歴史経験を結び合わせる。
研究目的・意義・期待される効果など
本研究の目的は、東南アジア大陸部冷戦期の文化と国家について、社会に埋め込まれた文化的諸要素に注目して、日常を生きる人々の歴史体験に真摯に向き合う「地べた」の冷戦史を描き出すことである。同時に、その中から近代化に逆行する草の根保守思想が冷戦/ベトナム戦争下の東南アジアにおいていかに顕在化していたのかも明らかにする。
タイとベトナムは、これまでイデオロギーという点で対極に位置付けられてきた。このイデオロギー上の問題を意図的に議論から退け、大衆日常的な文化的事象から両国の人々の歴史体験の並行性や連動性を、草の根保守思想に着目して見出そうとしている点が本研究の独自性といえる。
その方法論として、近年の冷戦研究に関する新たな議論を参考にしつつ、冷戦の二極化構造の秩序を最も形づけたベトナム戦争とその余波を受けたタイの冷戦に焦点を合わせる。その共通視座をもとに両地域の社会に埋め込まれた文化的諸要素(e.g. 宗教儀礼、伝統医療、山茶栽培、王の行幸)を見つめることにより、歴史経験の関連性を考え、東南アジア冷戦期を再考する。
本共同研究会の具体的な研究活動として、従来の二極化された冷戦史観を、いずれの極にも属さなくなった亡霊に注意を向けることで、より人びとの経験に根差した歴史の解釈に導くHeonik KwonのGhosts of War in Vietnamの輪読会を行う。その上で、各々のテーマを「地べた」という共通視座をさらに発展させ、まずは京都または東京で国際ワークショップを実施する。最終的には次年度、英文学術論文の投稿を目指す。